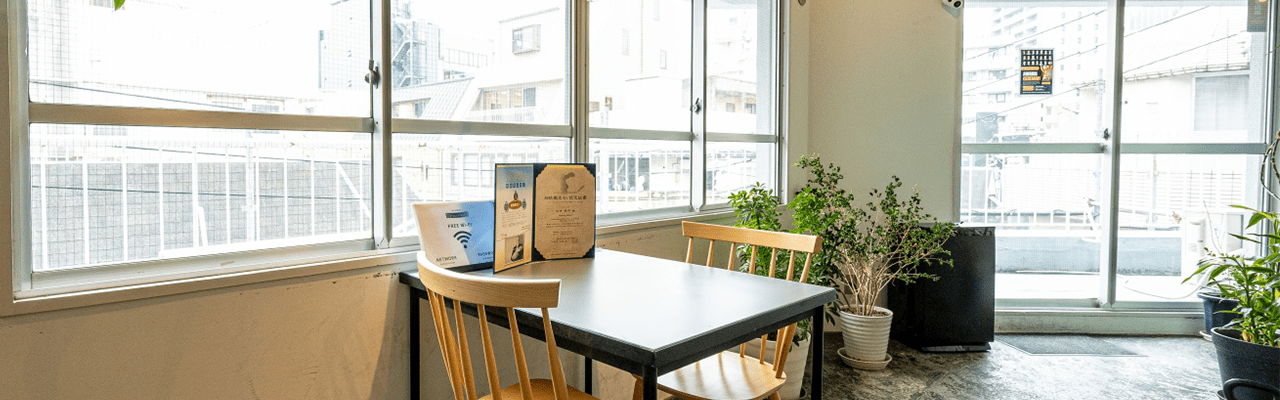
相続開始・・・最初にすべきことと注意点:スムーズな手続きのための完全ガイド
相続は、誰にとっても突然訪れる可能性のある出来事です。大切な人を失った悲しみの中、様々な手続きを迅速に進める必要があります。しかし、相続手続きは複雑で、期限付きのものも多く、何から手をつければ良いか分からず不安に感じる方も多いでしょう。
そこで本記事では、相続開始時に最初にすべきことと、注意すべきポイントを分かりやすく解説します。この記事を読めば、相続手続きの流れを把握し、スムーズに進めることができるでしょう。
1. 死亡の確認と死亡届の提出:7日以内の手続き
まず、病院で発行された死亡診断書を受け取り、死亡の事実を確認します。その後、7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。死亡届の提出は、故人の戸籍謄本などが必要です。
注意点:
- 死亡届の提出期限は7日以内と短いため、早めに準備しましょう。
- 死亡届の提出と同時に、火葬許可証の申請も行います。
2. 遺言書の有無の確認:自筆証書遺言は検認が必要
故人が遺言書を残している場合、その内容に従って遺産分割が行われます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
注意点:
- 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要です。検認前に開封すると、過料が科される可能性があります。
- 公正証書遺言と秘密証書遺言は、検認の必要はありません。
3. 相続人の確定と相続財産の調査:3ヶ月以内が目安
相続手続きを進める上で、誰が相続人になるのかを確定する必要があります。戸籍謄本などを収集し、法定相続人を特定します。
注意点:
- 相続放棄・限定承認の期限は、相続開始を知ってから3ヶ月以内です。相続財産の調査は早めに開始しましょう。
- 相続財産には、預貯金、不動産、有価証券、借金などが含まれます。漏れがないように、徹底的に調査しましょう。
4. 相続放棄・限定承認の検討:3ヶ月以内の選択
相続財産に借金が多い場合などは、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。相続放棄は、一切の財産を相続しない選択です。限定承認は、プラスの財産の範囲内で借金を相続する選択です。
注意点:
- 相続放棄・限定承認は、原則として撤回できません。慎重に検討しましょう。
- 家庭裁判所への申述が必要です。
5. 遺産分割協議:相続人全員で合意形成
遺言書がない場合、または遺言書の内容に不満がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割の方法や割合について、話し合いで決定します。
注意点:
- 遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
- 協議内容を書面に残し、後日のトラブルを防ぎましょう。
6. 相続税の申告と納税:10ヶ月以内の手続き
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
注意点:
- 相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。
- 相続税の申告期限は厳守しましょう。遅れると、延滞税や加算税が課される可能性があります。
7. その他必要な手続き
上記以外にも、故人の公共料金やクレジットカードの解約、不動産の名義変更など、様々な手続きが必要です。各手続きには期限がある場合があるので、早めに確認しましょう。
スムーズな相続手続きのための5つのポイント
- 早めの準備: 相続はいつ発生するか分かりません。生前から相続について話し合い、準備を進めておくことが大切です。
- 専門家への相談: 相続手続きは複雑なため、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
- 期限の確認: 各手続きには期限があります。期限を過ぎると、不利益を被る可能性があるので、必ず確認しましょう。
- 情報収集: 相続に関する情報は、書籍やインターネットなどで収集できます。最新の情報を入手し、手続きに役立てましょう。
- 記録の作成: 各手続きの記録を残しておくことで、後日のトラブルを防ぐことができます。
相続手続きは専門家へ相談しましょう
相続手続きは、複雑で時間と労力を要する作業です。特に、相続放棄・限定承認や相続税の申告など、期限付きの手続きは専門的な知識が必要となります。専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。相続で揉めることがあるようなら弁護士、相続税がかかりそうであれば税理士、不動産の相続があるようであれば司法書士があります。ただ、ご自身の置かれる状況がどれに当てはまるのかわからない場合がほとんどですので、まずは行政書士に相談するのがおススメです。
まとめ
相続開始時は、悲しみに暮れる間もなく、様々な手続きに追われることになります。しかし、慌てずに一つずつ手続きを進めていくことが大切です。本記事を参考に、相続手続きの流れを把握し、スムーズな手続きを実現してください。

