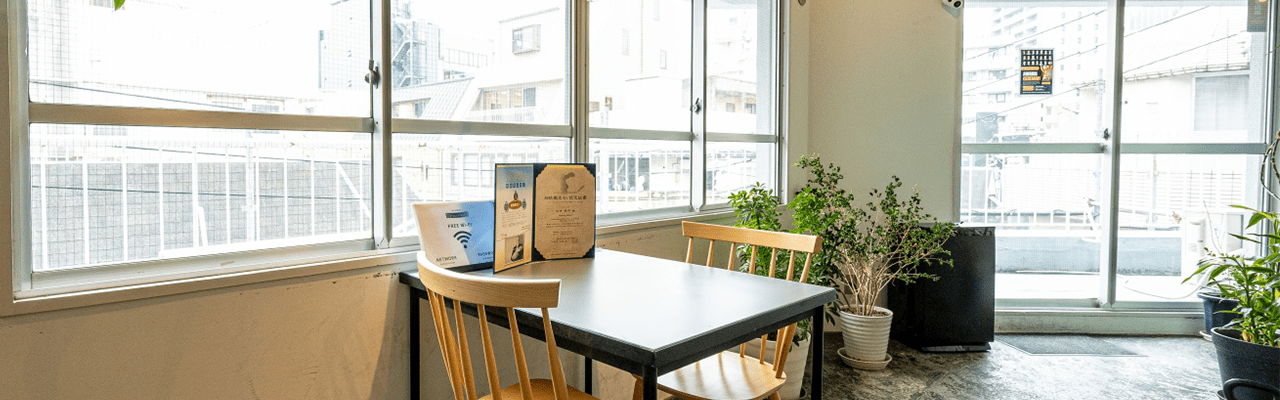
現代日本における遺言作成の重要性:特に遺言を推奨される方々について 第2回
第3章:遺言作成が特に推奨されるケース
法定相続のルールは一律ですが、個々の家庭状況や財産内容は様々です。そのため、法定相続に委ねるのではなく、遺言によって意思を明確にしておくことが強く推奨されるケースが数多く存在します。
3.1 家族構成に基づくケース
- 子供がいない夫婦:
子供がいない夫婦の一方が亡くなった場合、遺言がなければ、生存配偶者に加えて、亡くなった方の親(または祖父母)が存命であればその親が、親が既に亡くなっていれば兄弟姉妹(または甥・姪)が法定相続人となります 。多くの夫婦は、残された配偶者に全財産を相続させたいと考えるでしょうが、遺言なしではそれが実現できない可能性があります。特に、相続人が配偶者と兄弟姉妹になるケースでは、配偶者の法定相続分は3/4、兄弟姉妹が1/4となります 。これにより、例えば夫婦で築き上げてきた自宅不動産なども、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹との共有になる可能性があり、遺産分割協議が必要となります 。兄弟姉妹との関係が疎遠であったり、面識がなかったりする場合、協議が難航し、最悪の場合、配偶者が住み慣れた家を手放さなければならない事態も起こり得ます。
しかし、民法上、兄弟姉妹には遺留分(最低限保障される相続分)が認められていません 。したがって、「全財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹から遺留分を請求される心配はなく、確実に全ての財産を配偶者に遺すことができます。このように、子供がいない夫婦にとって遺言書は、残された配偶者の生活基盤を守り、望まない相続人との煩雑な手続きや争いを回避するために、不可欠とも言える法的手段です。 - 相続人が配偶者のみ、または血族相続人がいない/疎遠な場合:
配偶者以外に法定相続人となる血族がいない、あるいはいても関係が疎遠で財産を遺したくない場合、遺言がなければ、配偶者が全財産を相続します(配偶者のみの場合)。しかし、配偶者も子も親も兄弟姉妹もいない(または全員が先に死亡している)場合で、代襲相続する甥・姪などもいない場合は、法定相続人が不存在となります。この場合、特別な関係にあった人(特別縁故者、例えば内縁の配偶者など)が家庭裁判所に申し立てて財産分与を受けられる可能性もありますが、手続きは複雑で必ず認められるとは限りません 。最終的に相続人が確定しない財産は、国庫に帰属することになります 。
したがって、お世話になった人、長年連れ添った内縁のパートナー、友人、あるいは支援したいNPO法人や母校など、法定相続人以外に財産を遺したいと考える場合は、遺言書を作成し、遺贈の意思を明確に示しておく必要があります 。 - 再婚しており、連れ子がいる場合:
再婚相手が前のパートナーとの間にもうけた子供(連れ子)は、再婚相手(実親)の相続においては当然相続人となりますが、継親(再婚相手の配偶者)との間では、法律上の親子関係は自動的には発生しません。そのため、継親が亡くなった場合、養子縁組の手続きをしていない限り、連れ子は法定相続人にはなれません 。たとえ長年同居し、実の親子同然の関係を築いていたとしても、相続権は認められないのです 。
連れ子にも財産を遺したいと考える場合、主な方法は以下の3つです 。
- 養子縁組をする: 養子縁組をすれば、連れ子は法律上の子(嫡出子)となり、実子と同じ法定相続分を持ちます 。
- 遺言で遺贈する: 養子縁組は望まないが財産は遺したいという場合、遺言書に「○○(財産)を連れ子△△に遺贈する」と記載することで、財産を渡すことができます 。この場合、連れ子は「相続人」ではなく「受遺者」となります。記載方法として「相続させる」ではなく「遺贈する」を用いる点に注意が必要です。
- 生前贈与をする: 生前に財産を贈与しておく方法もあります。 遺言は、特に実子もいる場合に、実子と連れ子への財産の配分バランスを調整する手段としても有効です。ただし、実子には遺留分があるため、遺言を作成する際にはその点に配慮する必要があります 。
- 内縁関係のパートナーがいる場合:
法律上の婚姻届を提出していない内縁関係(事実婚)のパートナーは、どれだけ長期間生計を共にし、夫婦同然の生活を送っていても、法律上の配偶者ではないため、法定相続人にはなれません。したがって、遺言がなければ、パートナーは一切の財産を相続することができません。
内縁のパートナーに財産を遺すためには、遺言書を作成し、「○○(財産)を内縁の妻(夫)△△に遺贈する」と明確に指定することが、唯一かつ確実な方法となります 。この場合も、「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載します。
3.2 個人の意向に基づくケース
- 特定の相続人に財産を多く/少なく相続させたい、または相続させたくない場合:
法定相続分とは異なる割合で財産を分配したい場合、遺言による指定が必要です。例えば、家業を継ぐ長男に多めに財産を遺したい、あるいは特定の相続人には財産を渡したくない、といった意向を実現できます。
ただし、相続させたくない相続人が配偶者、子、または直系尊属である場合、その相続人には遺留分があるため、遺言で相続分をゼロとしても、遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります 。完全に相続権を奪うためには、生前の虐待や著しい非行などを理由に家庭裁判所に「相続人の廃除」を申し立てるか(遺言による廃除も可能)、その相続人に遺留分を放棄してもらう(家庭裁判所の許可が必要)といった手続きが必要になります 。一方で、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で「兄弟姉妹には相続させない」と指定すれば、その通りに実現されます 。 - 法定相続人以外の人や団体に財産を遺したい場合:
前述の通り、恩人、友人、内縁の配偶者、子の配偶者(例:息子の嫁)、あるいはNPO法人、母校、世話になった施設など、法定相続人ではない個人や団体に財産を遺贈したい場合は、遺言書を作成することが唯一の方法です 。 - 特定の財産を特定の相続人に承継させたい場合:
「自宅不動産は妻に、預貯金は長男に、有価証券は長女に」というように、どの財産を誰に相続させるかを具体的に指定したい場合も、遺言が必要です。これにより、遺産分割協議における「どの財産を誰がもらうか」という争いを未然に防ぎ、スムーズな財産承継を促すことができます。
3.3 保有資産の種類・状況に基づくケース
- 不動産(特に分割しにくいもの)を所有している場合:
不動産は、預貯金のように物理的に分割することが困難です 。遺言がない場合、法定相続分に従って相続人が共有することになる可能性がありますが、共有状態は管理や処分に関する意思決定が複雑になり、将来的にさらなるトラブル(共有者の死亡による権利関係の複雑化など)を招くリスクがあります。また、不動産の評価額を巡って相続人間で意見が対立したり 、誰がその不動産を取得するかで争いになったりすることも少なくありません 。特に自宅など、特定の相続人が居住している場合は、感情的な対立も絡みやすくなります。
不動産の相続は、単に経済的価値を移転するだけでなく、生活の基盤や家族の思い出といった感情的な要素も伴うため、法定相続による機械的な分割が必ずしも適切とは言えません。遺言によって、特定の相続人に単独で相続させる、売却して金銭で分割する(換価分割)、あるいは特定の相続人が取得する代わりに他の相続人に金銭を支払う(代償分割)といった具体的な方法を指定することで、このような不動産特有の問題を回避し、被相続人の意思に基づいた円満な解決を図ることが可能になります 。 - 自社株(非公開株式)を所有している場合:
中小企業の経営者などが自社株を所有している場合、遺言がないと、法定相続によって株式が後継者以外の相続人にも分散してしまう可能性があります 。株式が分散すると、後継者が会社の経営に必要な議決権(通常は過半数、重要な意思決定には2/3以上)を確保できなくなり、経営の安定性が損なわれたり、他の株主から経営に干渉されたりするリスクが生じます。
円滑な事業承継を実現するためには、経営者が生前に後継者を定め、その者に自社株を集中して相続させる旨の遺言書を作成しておくことが極めて重要です。ただし、他の相続人の遺留分への配慮(例えば、株式以外の財産を他の相続人に多く渡す、生命保険金を活用して遺留分侵害額請求に備えるなど)や、高額になりがちな自社株の相続税対策も併せて検討する必要があります 。 - 多額の預貯金、有価証券、美術品など、特定の分け方をしたい資産がある場合:
特定の資産について、特定の人に譲りたい、あるいは特別な分け方をしたいという希望がある場合も、遺言で指定することが有効です。遺産分割協議の手間を省き、被相続人の意図通りの分配を実現できます。
3.4 紛争予防・円滑な相続実現のためのケース
- 相続人間で不仲、または紛争が予想される場合:
相続人の間で既に関係が悪化している、あるいは将来的に遺産分割を巡って争いになる可能性が高いと予想される場合には、遺言書を作成しておくことが強く推奨されます。遺言で財産の分け方を明確に指定しておくことで、相続人同士が話し合う(遺産分割協議)の必要性を減らし、感情的な対立や法的な紛争に発展するリスクを低減する効果が期待できます。 - 特定の相続人に確実に財産を承継させたい場合:
例えば、障がいを持つ子の将来の生活資金を確保したい、献身的に介護をしてくれた子に報いたい、家業を継ぐ子に必要な事業用資産を確実に引き継がせたいなど、特定の相続人の状況や貢献に配慮し、財産を確実に承継させたいと考える場合、遺言はその意思を実現するための具体的な手段となります。 - 相続手続きをスムーズに進めたい場合:
遺言書があり、特に後述する「遺言執行者」が指定されていれば、相続発生後の預貯金の解約・払い戻し、不動産の名義変更(相続登記)、株式の名義書換といった煩雑な相続手続きが、相続人全員の協力や同意なしに、より迅速かつ円滑に進められる可能性が高まります。
第4章:遺言作成の実務と注意点
遺言書を作成する際には、その効力を確実にし、意図した通りの結果をもたらすために、いくつかの重要な実務上の点と注意点があります。
4.1 遺言の有効性確保
作成した遺言書が法的に有効と認められるためには、民法で定められた方式・要件を厳格に遵守する必要があります。
- 方式要件の遵守: 第2章で述べた各遺言方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)には、それぞれ満たすべき要件があります。特に自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の自書と押印が必須であり、一つでも欠けると無効となる可能性が高いです 14。日付は「令和○年○月○日」のように具体的に特定する必要があり、「○月吉日」のような記載は無効とされます 。押印は認印でも構いませんが、後日の紛争を避けるためには実印の使用が望ましいとされます 。公正証書遺言や秘密証書遺言における証人の要件(未成年者や推定相続人、受遺者などは証人になれない等)も遵守が必要です。
- 意思能力の確保: 遺言作成時に、遺言者が遺言の内容とその結果を理解・判断できる意思能力を有していることが、遺言の有効性の前提となります。認知症等で意思能力が疑われる状態で作成された遺言は、後にその有効性が争われるリスクがあります。この点、公正証書遺言は作成時に公証人が意思能力を確認するため、有効性が争われにくいという利点があります。
4.2 遺留分制度への配慮
遺言によって自由に財産配分を指定できますが、「遺留分」という制度による制約があります。
- 遺留分とは: 兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に対して、法律上最低限保障されている遺産の取り分です。これは、被相続人の財産形成への貢献や、残された遺族の生活保障といった観点から設けられています。
- 遺留分割合: 遺留分として保障される割合(総体的遺留分)は、相続人の構成によって異なります。
- 直系尊属(父母や祖父母)のみが相続人の場合:相続財産の1/3
- それ以外の場合(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属):相続財産の1/2 各相続人の個別の遺留分額は、この総体的遺留分に、各自の法定相続分割合を乗じて算出します 。例えば、相続人が配偶者と子1人の場合、総体的遺留分は1/2、配偶者の法定相続分は1/2、子の法定相続分は1/2なので、それぞれの遺留分は「相続財産 × 1/2 × 1/2 = 相続財産の1/4」となります 。
- 遺留分侵害額請求: 遺言や生前贈与によって自己の遺留分が侵害された相続人は、遺留分を侵害している他の相続人や受遺者(遺贈を受けた人)に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求権)。遺留分を侵害する内容の遺言自体が直ちに無効になるわけではありませんが 、この請求権が行使されると、金銭的な紛争に発展する可能性があります。この請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、または相続開始の時から10年間行使しないと時効等により消滅します。
- 遺留分対策: 遺留分を巡る争いを避けるためには、遺言作成時に以下の点を考慮することが有効です。
- 遺留分に配慮した内容にする: 可能な限り、各相続人の遺留分を侵害しないような財産配分を検討します。
- 付言事項の活用: 遺言書に付言事項として、なぜそのような財産配分にしたのか理由や想いを記し、相続人に理解を求めることで、遺留分請求を思いとどまらせる心理的効果を期待します 。
- 生命保険金の活用: 死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とみなされ、遺留分算定の基礎となる相続財産には含まれません 。特定の相続人に多くの財産を遺したい場合、その相続人を受取人とする生命保険に加入しておくことで、遺留分対策となり得ます 。
- 生前贈与の活用: 相続人以外への生前贈与は、原則として相続開始前1年以内に行われたもののみが遺留分算定の基礎に含まれます。相続人への贈与(特別受益にあたるもの)は、原則として相続開始前10年以内に行われたものが含まれます 31。これらのルールを理解した上で計画的に行う必要があります。
- 遺留分の事前放棄: 相続開始前に、遺留分権利者に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄してもらう方法もありますが、放棄する側の自由な意思と合理的な理由、相応の代償などが要件となります。
遺留分制度は、遺言者の意思(遺言自由)と、残される相続人の権利(生活保障等)とのバランスを図るための重要な仕組みです。遺言を作成する際には、この制度の存在を理解し、可能な範囲で配慮を示すことが、死後の無用な紛争を避け、遺言者の真意を円滑に実現するための鍵となります。遺留分を完全に無視した遺言は、かえって相続人間の対立を招き、遺言に込めた想いが実現されない結果にも繋がりかねません。
4.3 遺言執行者の指定
遺言の内容を具体的に実現するための手続きを行うのが「遺言執行者」です。
- 遺言執行者とは: 相続開始後、遺言書の内容に従って、相続財産の管理、名義変更(不動産登記、預貯金解約など)、遺産の分配といった、遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限と義務を持つ者です 。
- 指定方法: 遺言書の中で、「遺言執行者として○○を指定する」といった形で指名することができます。第三者に指定を委託することも可能です。
- 役割と義務: 遺言執行者に就任した場合、遅滞なくその旨と遺言の内容を全相続人に通知する義務があります。また、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付する義務も負います。
- 指定のメリット: 遺言執行者がいると、相続手続きが格段にスムーズに進みます。遺言執行者は、相続人全員の同意や協力を得なくても、単独で預貯金の解約や不動産の名義変更などの手続きを行う権限を持ちます。特に、相続人が多数いる場合、相続財産が複雑な場合、遺贈(相続人以外への財産譲渡)がある場合、相続人の廃除や子の認知など遺言でしかできない事項が含まれる場合、あるいは相続人間に対立があり協力が期待できない場合には、遺言執行者の指定が極めて有効です。
- 誰を指定するか: 未成年者と破産者以外であれば、特別な資格は不要で、相続人の一人を指定することも、信頼できる友人や知人を指定することも可能です 。しかし、手続きの専門性や相続人間の公平性を考慮すると、弁護士や行政書士といった法律専門家を遺言執行者に指定することも有力な選択肢です。専門家を指定する場合、通常は報酬が発生し、相続財産の中から支払われます。
遺言執行者の指定は、いわば遺言内容を実現するための「実行部隊」を予め任命しておく行為です。遺言書を作成するだけでなく、その内容を確実に実現させるためには、遺言執行者の指定が非常に重要となります。特に、遺言の内容が複雑であったり、相続人間での対立が予想されたりする場合には、中立的かつ専門的な立場から手続きを進めることができる専門家を遺言執行者に指定することが、公平で円滑な遺言執行を実現するための鍵と言えるでしょう 。
4.4 付言事項の活用
遺言書には、法的な効力を持つ本文とは別に、「付言事項」として、遺言者の想いやメッセージを書き添えることができます。
- 付言事項とは: 遺産の分配方法を指定するような法的拘束力はありませんが、なぜそのような遺言内容にしたのかの理由、各相続人への感謝の言葉、残される家族への願いなどを自由に記載できる部分です。
- 効果: 付言事項を通じて遺言者の真意や想いを伝えることで、相続人が遺言の内容に納得しやすくなり、感情的な対立や紛争を抑制する心理的な効果が期待できます。特に、法定相続分と異なる配分をする場合や、遺留分を侵害する可能性がある場合には、その理由を丁寧に説明しておくことが、円満な相続の実現に繋がる可能性があります。ただし、付言事項に何を書いても自由ですが、特定の相続人への誹謗中傷など、かえって感情を逆なでするような内容は避けるべきです。
4.5 遺言作成・見直しのタイミング
- 作成可能年齢: 満15歳以上であれば、誰でも遺言書を作成できます 。
- 推奨されるタイミング: 遺言書作成に「早すぎる」ということはありません 。一般的には高齢になってから考える人が多いですが 、死期は誰にも予測できません。突然の事故や病気のリスクは若年層にも存在します。したがって、最も重要なのは、心身ともに健康で、判断能力がしっかりしているうちに作成しておくことです。「思い立ったが吉日」であり、先延ばしにしないことが肝心です。
- 具体的なきっかけ: 遺言書作成を考えるきっかけは人それぞれですが、以下のようなタイミングが挙げられます。
- ライフイベント: 就職、結婚、子供の誕生、住宅の購入、離婚・再婚、子供の独立、定年退職、配偶者との死別など、家族構成や生活環境が大きく変化した時。
- 健康状態の変化: 自身の高齢化を意識した時 、大きな病気や怪我をした時、健康診断で気になる結果が出た時、あるいは余命宣告を受けた時 など、自身の健康に不安を感じた時 。
- 財産状況の変化: 親からの相続、退職金の受給、事業の開始や拡大など、財産の内容や規模が変動した時。
- 人間関係の変化: 家族や親族間でトラブルが生じた時、あるいは将来的な紛争を懸念した時 。
- 定期的な見直しの必要性: 遺言書は一度作成したら終わりではありません。作成後に、家族構成(子の結婚、孫の誕生など)、財産状況(資産の増減、不動産の売買など)、人間関係、あるいは自身の考え方が変化することは十分にあり得ます。また、相続に関する法律や税制が改正されることもあります。そのため、作成した遺言書の内容が現状に適合しているか、定期的に(例えば数年ごとや、大きなライフイベントがあった際などに)見直しを行い、必要であれば新しい内容で書き換える(変更・撤回する)ことが非常に重要です。
第5章:専門家への相談の重要性
遺言書の作成は、法的な要件や考慮すべき点が多岐にわたるため、専門家への相談が非常に有益です。
5.1 なぜ専門家への相談が必要か
- 法的有効性の確保: 遺言書は厳格な方式要件を満たさなければ無効となります。専門家は、選択した方式に応じた要件を確実に満たすようサポートし、遺言の有効性を担保します。
- 最適な内容の検討: 個々の家族構成、財産状況、そして何よりも遺言者の意思を正確に反映し、かつ将来の紛争リスクを最小限に抑えるような最適な遺言内容を、法的な観点からアドバイスします。
- 複雑な問題への対応: 遺留分への配慮、相続税の試算と対策、不動産の評価や分割方法の検討、自社株を含む事業承継計画との整合性など、専門的な知識が必要となる複雑な問題に対応できます 。
- 紛争リスクの低減: 専門家が関与して作成された遺言書は、内容の明確性や公平性、法的な妥当性が高まり、相続人間の無用な疑念や争いを未然に防ぐ効果が期待できます 。
たとえ費用を抑えたいと考えて自筆証書遺言を選択する場合であっても、その内容については事前に専門家に相談し、法的な問題点や潜在的なリスクについてアドバイスを受けておくことが強く推奨されます。
5.2 相談できる専門家:
遺言や相続に関して相談できる主な専門家として、弁護士と司法書士が挙げられます。それぞれ業務範囲や得意分野が異なります。
- 弁護士 :
- 業務範囲: 法律事務全般を取り扱うことができます。遺言書の作成相談・起案・作成はもちろん、相続発生後の遺産分割協議の代理交渉、家庭裁判所での遺産分割調停・審判や遺留分侵害額請求訴訟などの代理人活動、遺言執行者としての業務など、相続に関するあらゆる法的問題に対応可能です 。
- 強み: 最大の強みは、相続人間の紛争が発生した場合(またはその可能性がある場合)に、代理人として交渉や法的手続き(調停・訴訟)を行える唯一の専門家である点です。包括的な法的アドバイスを提供できます。
- 相談が推奨されるケース: 相続人間で既に対立がある、または将来的に紛争が予想される場合。遺産の内容が複雑(多額の借金、海外資産、複雑な権利関係の不動産など)な場合。遺留分の問題が深刻化しそうな場合。事業承継が絡む場合。
この他に、行政書士は書類作成の専門家として、遺言書の作成支援や、既に合意済みの遺産分割協議書作成などを行いますが、紛争案件や登記、訴訟代理は扱えません 。司法書士は不動産登記が必要な場合に相談することになります。税理士は、相続税の計算や申告、節税対策に関する専門家です 。
どの専門家に相談すべきかは、個々の事案の性質(紛争の可能性、財産の種類、税金の懸念など)によって異なります。しかし、相続は潜在的に紛争リスクを内包していることが多く、また遺留分や税金など法的に複雑な問題が絡むことも少なくありません。そのため、少しでも紛争の可能性がある、あるいは法的な論点が複雑であると感じる場合には、最初から広範な法的問題に対応でき、唯一紛争解決の代理権を持つ弁護士に相談することが、結果的に最も安全かつ効率的な解決に繋がる可能性が高いと言えます。まずは1番身近に相談可能な行政書士に依頼すれば、必要に応じて弁護士や司法書士、税理士と連携し、登記や税務の問題も含めてワンストップで対応してもらえることも多いです 49。
5.3 専門家選びのポイントと費用
- 選び方: 専門家を選ぶ際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。
- 経験と実績: 相続・遺言分野における経験が豊富か、具体的な解決実績があるかを確認します 。
- 費用の明確性: どのような業務にどれくらいの費用がかかるのか、事前に明確な説明や見積もりを提示してくれるかを確認します 。
- 相性: 信頼して任せられるか、話しやすいか、説明が分かりやすいかなど、実際に相談してみて相性を確かめることも重要です 。多くの事務所で初回無料相談などを実施しているので、活用すると良いでしょう 。
結論
現代の日本社会において、遺言書は、単に死後の財産配分を決めるためだけではなく、多様化する家族関係や複雑化する資産状況に対応し、自らの最終意思を明確に実現するための重要な法的ツールとなっています。特に、以下のような状況にある方々にとっては、遺言書の作成は単なる選択肢ではなく、強く推奨される、あるいは不可欠な準備と言えます。
- 子供がいない夫婦: 残された配偶者の生活を守り、望まない親族との遺産分割協議を避けるために必須。
- 再婚家庭や内縁関係にある方: 法律上の相続権がない連れ子や内縁パートナーに財産を遺す唯一確実な方法。
- 事業経営者(特に自社株所有者): 円滑な事業承継を実現し、会社の経営安定を図るための鍵。
- 不動産(特に分割しにくいもの)を所有する方: 共有状態の回避や評価額を巡る争いを防ぎ、意図した承継を実現するため。
- 法定相続人以外に財産を遺したい方: 恩人、友人、団体などへの遺贈の意思を実現するため。
- 相続人間の不和が予想される方: 遺産分割を巡る紛争を未然に防ぎ、円満な相続を促すため。
- 特定の相続人に特定の財産を確実に遺したい、または法定相続分と異なる配分を望む方。
遺言書を作成することは、自らの人生の締めくくり方について主体的に意思決定を行うことであり、残される家族や大切な人々への最後の配慮を示す行為でもあります。それは、無用な争いを防ぎ、円滑な財産承継を可能にするための、最も有効な手段の一つです。
ただし、遺言書の作成には、厳格な法的要件の遵守、遺留分制度への配慮、相続税の問題など、専門的な知識が求められる側面も少なくありません。したがって、自らの意思を確実に、かつ法的に有効な形で実現するためには、安易に自己判断せず、弁護士や行政書士などの専門家に相談し、個々の状況に応じた最適なアドバイスを受けながら、適切な遺言書を作成することが極めて重要です。元気なうちに、そして思い立った時に、専門家のサポートを得て遺言作成に取り組むことが、将来の安心に繋がる賢明な選択と言えるでしょう。

