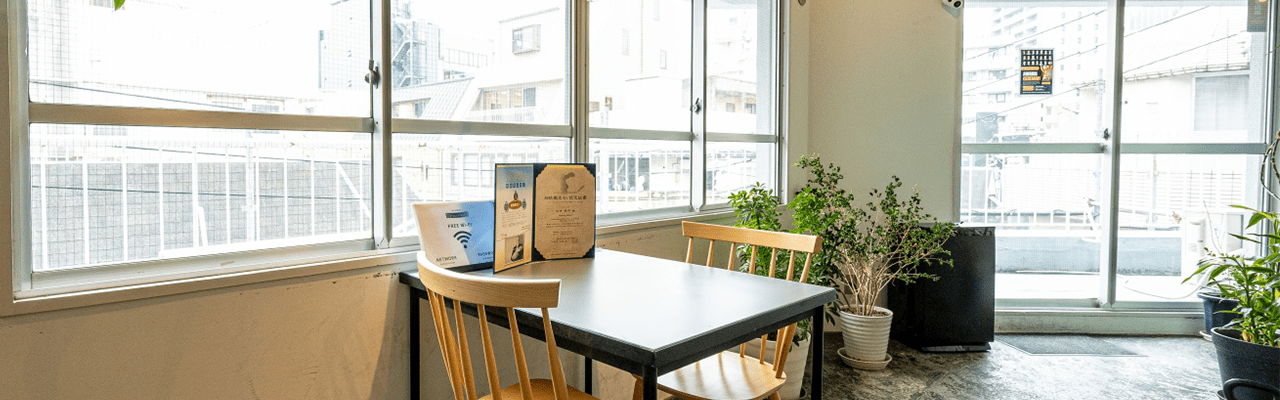
現代日本における遺言作成の重要性:特に遺言を推奨される方々について 第1回
はじめに
現代の日本社会においては、家族形態の多様化や資産内容の複雑化に伴い、相続を巡る状況は以前にも増して複雑化しています。このような状況下で、自らの死後に発生する財産承継について、生前の意思を明確に示しておく「遺言」の役割はますます重要になっています。
遺言がない場合、民法が定める「法定相続」のルールに従って遺産は分配されます。しかし、この法定相続のルールは画一的であり、必ずしも個々の家庭の事情や、亡くなった方(被相続人)の真の意向を反映するものとは限りません。特に、法定相続人ではないものの生前に深い関わりがあった人物へ財産を遺したい場合や、相続人間での争いを避けたい場合など、法定相続の原則だけでは対応できないケースが多く存在します。
民法の規定に基づき、どのような状況にある人が特に遺言を作成することが推奨されるのかを、年齢、家族構成、保有資産、個人の意向といった具体的な要素を踏まえながら、法的な観点から詳細に分析・解説することを目的とします。遺言によって、法定相続とは異なる財産配分や、特定の人物への財産の承継を指定することが可能となり、自らの意思を死後においても実現するための有効な手段となります 。本レポートを通じて、遺言作成の必要性についての理解を深め、ご自身の状況に照らして適切な準備を進めるための一助となれば幸いです。
第1章:遺言なき相続の原則:法定相続の基本ルール
遺言書が存在しない場合、相続は民法に定められたルール、すなわち「法定相続」に従って進められます。誰が相続人となり、どの程度の割合で遺産を受け取るのかは、法律によって明確に規定されています。
1.1 法定相続人:誰が相続するのか
法定相続人となれるのは、被相続人の配偶者と血族の一部に限られます 。
- 配偶者: 法律上の婚姻関係にある配偶者は、常に法定相続人となります。たとえ長期間別居していたとしても、法的に離婚が成立していなければ相続権を有します 。一方で、婚姻届を提出していない内縁関係のパートナーや事実婚の相手、離婚した元配偶者は、法定相続人にはなれません 。
- 血族相続人: 配偶者以外の血族相続人には、相続できる順位が定められています 。
- 第1順位:子およびその代襲相続人(孫など) 被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となります 1。実子だけでなく、養子縁組をした子や、認知した子も含まれます 。子が被相続人より先に死亡している場合は、その子(孫)が代わりに相続人となります(代襲相続)。孫も死亡している場合は、ひ孫が再代襲相続します 。
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など) 第1順位の相続人(子や孫など)がいない場合に限り、被相続人の父母が第2順位の相続人となります 。父母が共に死亡しており祖父母が健在の場合は、祖父母が相続人となります 。親等の近い者が優先されます 。養親も実親と同様に含まれますが、直系尊属には代襲相続はありません 。
- 第3順位:兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥・姪) 第1順位、第2順位の相続人がいずれもいない場合に限り、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります 。兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します 。ただし、兄弟姉妹の代襲相続はこの一代限りであり、甥や姪が死亡していても、その子が再代襲することはありません 。
上位の順位の相続人が一人でもいる場合、下位の順位の者は相続人になることはできません 。例えば、子がいる場合には、父母や兄弟姉妹は相続人にはなれません。
なお、法律上の配偶者や上記の血族相続人であっても、相続放棄をした人や、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った人は相続人とはなれません 。また、配偶者の親や兄弟姉妹(姻族)、いとこ、叔父叔母なども法定相続人には含まれません 。
1.2 法定相続分:遺産の取り分
法定相続人が受け取る遺産の割合(法定相続分)は、相続人の組み合わせによって民法で定められています。
表1.1:法定相続人と法定相続分の組み合わせ早見表
|
相続人の組み合わせ |
配偶者の相続分 |
血族相続人の相続分(合計) |
各血族相続人の取り分 |
|
配偶者と子 |
1/2 |
1/2 |
1/2を子の人数で均等割り |
|
配偶者と直系尊属 |
2/3 |
1/3 |
1/3を直系尊属の人数で均等割り |
|
配偶者と兄弟姉妹 |
3/4 |
1/4 |
1/4を兄弟姉妹の人数で均等割り(※) |
|
配偶者のみ |
1 (すべて) |
- |
- |
|
子のみ |
- |
1 (すべて) |
1を子の人数で均等割り |
|
直系尊属のみ |
- |
1 (すべて) |
1を直系尊属の人数で均等割り |
|
兄弟姉妹のみ |
- |
1 (すべて) |
1を兄弟姉妹の人数で均等割り(※) |
(※)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の相続分の1/2となります。
例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者の相続分は1/2、子の相続分は合計で1/2となり、子1人あたりでは1/4(=1/2÷2)となります。
この法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員が合意すれば、これと異なる割合で遺産を分割することも可能です(遺産分割協議)。しかし、相続人間で合意に至らない場合は、家庭裁判所での調停や審判によって分割方法が決定されることになり、紛争が長期化する可能性があります。
1.3 法定相続の限界と遺言の必要性
法定相続のルールは、血縁関係と法律上の配偶者関係を基準とした画一的なものです 。そのため、現代社会の多様な家族関係や個人の意思を十分に反映できない場合があります。
例えば、長年連れ添った内縁の妻や、献身的に介護をしてくれた子の配偶者、あるいは特定の友人や慈善団体に財産を遺したいと考えていても、これらの人々は原則として法定相続人ではないため、遺言がなければ財産を受け取ることはできません 。また、法定相続人の中に、関係性が希薄であったり、むしろ財産を渡したくないと考えている人物(例えば、疎遠な兄弟姉妹など)が含まれている場合もあります 。このような場合、法定相続のルールに従うと、被相続人の意に反する結果となってしまう可能性があります。
法定相続は、あくまで遺言がない場合の補充的なルールです。個々の事情や被相続人の真意を反映した財産承継を実現するためには、遺言書を作成し、自らの意思を明確に示しておくことが不可欠となります。法定相続の画一的なルールでは対応できない、個別の意思や特別な人間関係に基づく財産配分を可能にするのが、遺言の重要な役割の一つです。
第2章:意思を形に:遺言の法的効力と種類
遺言は、自らの死後の財産について最終的な意思を示す法的な文書です。適切に作成された遺言は、法定相続のルールに優先して適用され、個人の意向に沿った財産承継を実現する力を持っています。
2.1 遺言の優先効力
遺言書が存在する場合、原則としてその内容が法定相続よりも優先されます。つまり、遺言書で指定された通りに遺産が分配されることになります。これにより、以下のようなことが可能になります。
- 法定相続分と異なる相続分の指定: 特定の相続人により多くの財産を遺したり、逆に少なくしたりするなど、法定相続分とは異なる割合で相続分を指定できます。
- 法定相続人以外への財産の遺贈: 法定相続人ではない人物(例えば、内縁の配偶者、友人、恩人、子の配偶者など)や、法人・団体(NPO法人、母校、慈善団体など)に対して財産を遺すこと(遺贈)が可能です。
- 特定の財産の承継者の指定: 不動産や自社株など、特定の財産を特定の相続人に引き継がせたい場合、その旨を指定できます。
ただし、遺言の内容が完全に自由というわけではありません。後述する「遺留分」制度により、一定の法定相続人には最低限保障される遺産の取り分があり、遺言によってもこれを完全に奪うことはできません 。(詳細は第4章で解説します)。
2.2 遺言の種類と要件
日本の民法では、遺言の方式として主に「普通方式遺言」が定められており、これには自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります 。それぞれの方式には厳格な要件が定められており、これを満たさない遺言は無効となる可能性があります。
- 自筆証書遺言 :
遺言者が、遺言書の全文、作成日付、氏名をすべて自筆で書き、押印する方式です 14。パソコンでの作成や他人による代筆は認められません 。ただし、財産目録を添付する場合に限り、その目録は自書でなくても構いませんが、目録の各ページ(両面に記載がある場合は両面)に署名と押印が必要です 。
- メリット: いつでも手軽に、費用をかけずに作成できます 。内容を秘密にしておくことも可能です。
- デメリット: 法律で定められた要件を満たさない形式不備により、遺言が無効となるリスクが最も高い方式です 。また、遺言書そのものの紛失、盗難、隠匿、偽造、改ざんといったリスクも伴います。遺言者の死後、原則として家庭裁判所による「検認」という手続きが必要となり相続人に手間がかかります。
- 公正証書遺言 :
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え(口授)、公証人がそれを筆記して作成する方式です 。遺言者および証人が内容を確認し、署名・押印します 。
- メリット: 法律の専門家である公証人が作成に関与するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、最も確実な方式とされています。遺言書の原本は公証役場に厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。また、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
- デメリット: 作成のために公証役場へ出向く必要があり(出張も可能だが別途費用要 )、証人の手配や公証人への手数料など、手間と費用がかかります。また、遺言の内容が公証人と証人に知られることになります。
- 秘密証書遺言 :
遺言者が作成し署名・押印した遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いた印章で封印します。その封書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自己の遺言書である旨とその筆者の氏名・住所を申述する方式です。
- メリット: 遺言の内容を、作成時から公証人や証人にも秘密にしておくことができます。自筆証書遺言と異なり、本文はパソコン等で作成することも可能です 。
- デメリット: 遺言の内容自体は公証人が確認しないため、内容の不備によって無効となるリスクがあります 。作成手続きが他の方式に比べて煩雑であり、利用されるケースは非常に少ないのが現状です 。また、自筆証書遺言と同様に、死後に家庭裁判所での検認手続きが必要です 。
- 自筆証書遺言保管制度:
2020年から始まった制度で、作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます。
- メリット: 法務局が原本を保管するため、紛失・改ざんのリスクが大幅に軽減されます。また、この制度を利用した場合、家庭裁判所での検認が不要になります 。遺言者の死亡時には、指定された相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知を送るよう依頼することも可能です 。
- デメリット: 遺言書の内容に関する相談は法務局ではできません 。申請手続きは遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があり、代理申請は認められません 。また、用紙サイズや余白など、定められた様式で作成する必要があります 。保管申請には手数料(3,900円)がかかります 。
表2.1:遺言方式の比較
|
項目 |
自筆証書遺言(通常) |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
自筆証書遺言(保管制度利用) |
|
作成方法 |
全文・日付・氏名自書、押印 |
公証人が作成 |
本人作成、封印、公証/証人証明 |
全文・日付・氏名自書、押印(様式あり) |
|
証人 |
不要 |
2人以上必要 |
2人以上必要 |
不要 |
|
費用 |
ほぼ無料 |
有料(数万円~) |
有料(定額) |
有料(3,900円) |
|
手軽さ |
最も手軽 |
手間がかかる |
手間がかかる |
手間がかかる(要出頭) |
|
内容の秘密保持 |
可能 |
困難(証人等に知られる) |
可能 |
可能 |
|
有効性リスク |
高い(要式不備) |
極めて低い |
あり(内容不備) |
低い(外形チェックあり) |
|
紛失・改ざんリスク |
高い |
ほぼ無し |
低い(存在証明) |
ほぼ無し(法務局保管) |
|
検認要否 |
必要 |
不要 |
必要 |
不要 |
複数の遺言書が存在し、その内容が互いに矛盾・抵触する場合、日付が最も新しい遺言の内容が優先されます 。
2.3 遺言能力
遺言を有効に行うためには、遺言者に「遺言能力」が必要です。
- 年齢: 民法では、満15歳に達した者は遺言をすることができると定められています 。通常の法律行為(契約など)よりも低い年齢が設定されているのは、遺言が本人の最終意思を尊重する行為であるためです 。
- 意思能力: 遺言を作成する時点で、遺言の内容やそれによって生じる法的な結果を理解し、判断できる能力(意思能力)が必要です 。重度の認知症や精神疾患などにより、この意思能力が欠けていると判断される状態で作成された遺言は、後日無効とされる可能性があります 。
現代の日本は急速に高齢化が進行しており、それに伴い認知症を発症する人の数も増加しています。このような状況下では、遺言作成時の意思能力の有無が、相続発生後に遺言の有効性を巡る争いの大きな原因となり得ます 。特に自筆証書遺言の場合、作成時の状況を客観的に証明することが難しく、意思能力が争点となりやすい傾向があります。
これに対し、公正証書遺言は、作成プロセスにおいて公証人が遺言者の本人確認および意思能力の確認を行うため、後になって意思能力の欠如を理由に遺言の有効性が争われるリスクを大幅に低減できます 。したがって、加齢に伴う判断能力低下のリスクに備えるためには、心身ともに健康で判断能力が確かなうちに、証明力の高い公正証書遺言を作成しておくことが、自らの最終意思を確実に実現し、将来の相続争いを予防するための極めて有効な手段と言えます。
第2回に続きます。

