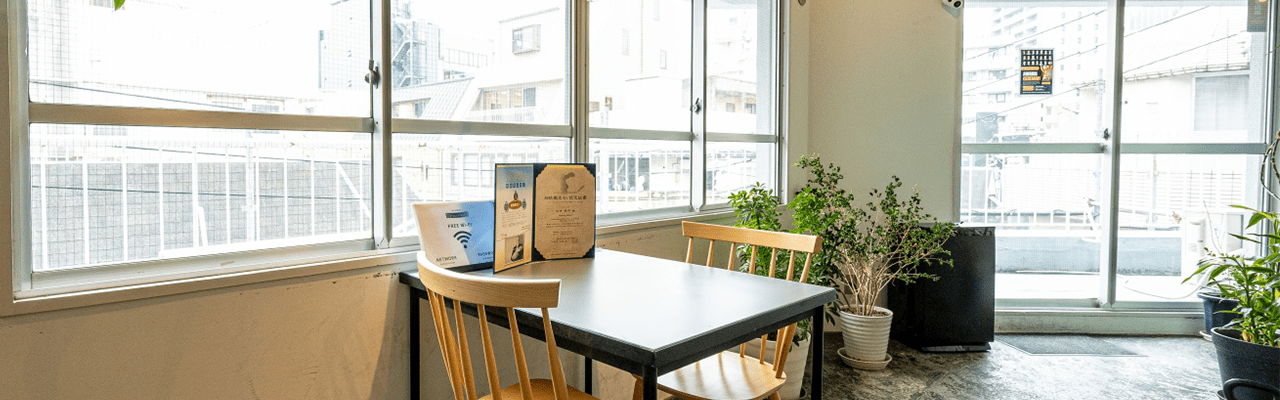
相続トラブル回避!口約束は危険?生前対策の重要性
相続は、家族にとって大きな転換期です。しかし、財産の分け方を巡って、親族間で感情的な対立が生まれ、深刻なトラブルに発展するケースも少なくありません。特に、被相続人が生前に残した「口約束」は、しばしば相続争いの火種となります。
今回は、口約束が原因で実際に起きたトラブル事例をいくつかご紹介し、遺言をはじめとした生前対策の重要性について解説します。
口約束が引き起こす相続トラブル事例
相続発生後、被相続人の生前の口約束が原因で、親族間で激しい争いに発展するケースは少なくありません。具体的な事例を通して、口約束の危険性を見ていきましょう。
事例1:長男への過度な期待が生んだ不平等感
地方で代々続く旧家を相続したAさんのケース。被相続人である父親は、生前長男のAさんに「お前が家と土地を継いで、家を守ってくれ」と繰り返し伝えていました。しかし、遺言書には具体的な指示はなく、法定相続分通りに分割されることになりました。
これに対し、Aさんは「父の口約束を信じて、これまで家のことを第一に考えてきた。兄弟たちは都会に出て、ほとんど実家には帰ってこなかったのに、同じように遺産を分けるのは不公平だ」と主張。一方、他の兄弟たちは「口約束はあくまで口約束。遺言書がない以上、法律に従うしかない」と反論。
感情的な対立は激化し、Aさんは他の兄弟たちを相手取り、不動産の所有権移転を求める訴訟を起こしました。裁判では、口約束の証拠能力が争点となり、最終的にはAさんの主張は認められず、法定相続分通りの分割となりました。
この事例からわかるように、被相続人の生前の期待や願望は、遺言書という形で明確に示されない限り、法的な効力を持たないということです。
事例2:介護の貢献度が評価されなかった悲劇
高齢の母親の介護を10年間献身的に行ってきたBさんのケース。母親は生前、「私の面倒をよく見てくれたあなたには、少し多めに財産を分けたい」とBさんに伝えていました。しかし、遺言書には具体的な金額の記載はなく、他の兄弟たちと法定相続分通りに分割されることになりました。
Bさんは、「母親の介護は本当に大変だった。他の兄弟たちはほとんど何もしてくれなかったのに、同じように遺産を分けるのは納得できない」と主張。しかし、他の兄弟たちは「介護は娘として当然のこと。遺言書がない以上、特別な配慮はできない」と反論しました。
感情的な対立は激化し、Bさんは他の兄弟たちを相手取り、寄与分を求める調停を申し立てました。調停では、Bさんの介護の貢献度が争点となり、最終的には寄与分が認められ、Bさんは法定相続分よりも多少多い遺産を取得することができました。
この事例からわかるように、介護の貢献度は、相続において一定の評価を受ける可能性があります。しかし、そのためには、具体的な証拠や客観的な評価が必要となります。
事例3:事業承継を巡る親族間の対立
父親が経営していた会社を継いだCさんのケース。父親は生前、「会社はお前に任せる。株式もすべてお前に譲る」とCさんに伝えていました。しかし、遺言書には株式の具体的な配分が記載されておらず、他の兄弟たちも法定相続分を主張しました。
Cさんは、「会社を維持・発展させてきたのは自分だ。他の兄弟たちは会社の経営には一切関わってこなかったのに、株式を要求するのはおかしい」と主張。一方、他の兄弟たちは「自分たちにも相続する権利がある。会社の将来よりも、自分たちの生活が大事だ」と反論。
感情的な対立は激化し、Cさんは他の兄弟たちを相手取り、株式の所有権確認訴訟を起こしました。裁判では、Cさんの会社の経営への貢献度や、他の兄弟たちの会社の経営への関与の有無が争点となり、最終的にはCさんの主張が認められ、Cさんは会社の株式の大部分を取得することができました。
口約束がトラブルに発展しやすい理由
これらの事例に共通するのは、被相続人の口約束が、法的な効力を持たないということです。口約束は、あくまで当事者間の合意であり、第三者に対する拘束力はありません。そのため、他の相続人たちが口約束の内容を知らなかったり、内容を認めなかったりする場合、トラブルに発展しやすいのです。
また、口約束は、内容が曖昧になりがちです。例えば、「多めに分け与える」という言葉は、人によって解釈が異なります。そのため、後になって「言った」「言わない」の水掛け論になり、収拾がつかなくなることもあります。
トラブル回避のための生前対策
このようなトラブルを回避するためには、遺言をはじめとした生前対策が不可欠です。
- 遺言書の作成
遺言書は、被相続人の最終的な意思を明確に示すための重要な書類です。遺言書を作成することで、口約束のような曖昧さを排除し、相続財産の分け方を具体的に定めることができます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、確実性を高めるためには、公正証書遺言がおすすめです。 - 家族信託の活用
家族信託は、財産の管理・運用・処分を信頼できる家族に託す制度です。家族信託を活用することで、高齢や認知症などで判断能力が低下した場合でも、財産を適切に管理し、希望する形で承継させることができます。 - 生前贈与の検討
生前贈与は、生きているうちに財産を譲り渡すことです。生前贈与を活用することで、相続財産の総額を減らし、相続税の負担を軽減することができます。ただし、贈与税が発生する可能性があるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。 - 専門家への相談
相続や遺言、家族信託などに関する悩みや疑問は、専門家への相談をおすすめします。弁護士、税理士、行政書士などの専門家は、豊富な知識と経験に基づき、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを提供してくれます。
行政書士に相談するメリット
特に、行政書士は、遺言書作成や家族信託契約書作成のサポート、相続手続きに関する相談など、幅広い業務に対応しています。行政書士は、法律の専門家であると同時に、地域に根差した身近な相談相手でもあります。そのため、相続に関する悩みや不安を気軽に相談することができます。
まとめ
相続は、誰にでも起こりうる身近な問題です。しかし、事前の準備を怠ると、深刻なトラブルに発展する可能性があります。大切な家族が争うことにならないよう、遺言をはじめとした生前対策を積極的に検討しましょう。
相続や遺言、家族信託などについて、ご不明な点やご不安なことがございましたら、お気軽に行政書士までご相談ください。

